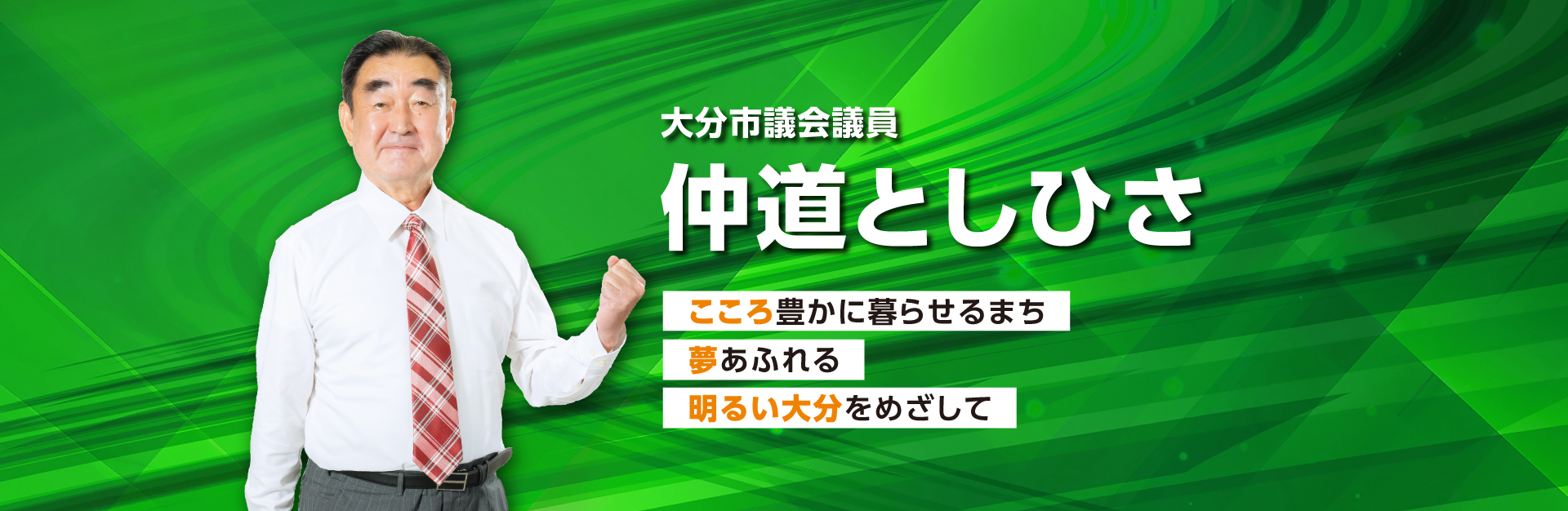『記念日』の後書きに次のように書かれていました。
【なお、記念という語は「祝賀を意味する日」以外にも使われる(例:終戦記念日)】
祝賀ではない日を『記念日』と表現することに、わたしの心はなかなか馴染んでくれません。祝賀という以外にどんな意味があるのか、記念の語源を検索してみました。
●過去の出来事や経験を心に浮かべるよすが(拠り所)となる物
●特別な出来事があったというしるし
●過去の出来事などへの思いを新たにすること
確かに、祝賀とは限定されていません。
きょう3月31日は教育基本法 公布記念日でした。例によってどんな祝賀?という気持ちで読んでいると、途中から雲行きが怪しくなってきました。
『1947年(昭和22年)3月31日、連合国軍 最高司令官 総司令部(GHQ)の占領統治下のもと、日本国憲法制定後の帝国議会によって教育基本法(以後 旧法という)が公布された。
旧法は、制定直後から改正論、及び改正論への反対論が何度も起こった。愛国心や伝統の尊重といった考え方が欠けているという改正賛成派と、復古的なナショナリズムや国家への奉仕の強要につながりかねないとする改正反対派の対立が繰り返されてきた。(中略)現行の教育基本法(2006年、平成18年12月22日公布)は、旧法の全部を改正したもの』
『教育基本法 公布記念日3月31日』は、旧法改正賛成派と反対派では何を記念するのか真逆の記念日だと思われます。わたし自身、きょうそして今後の○○記念日に『心に刻むもの』をしっかり・はっきり見極めていかなければいけないと思いました。例えばきょうであれば、2006年教育基本法全部改正は是か非か。
(としひさ)